確定申告がおわりました
簡単に手順を記しておきます
今年の確定申告
今年の確定申告はやや複雑です。
その理由は、
1 昨年3月まで、正社員で勤務していたのでその時の源泉徴収票がある
2 退職金が出ている
3 個人事業主になり、収入はほとんどないが経費がでた(仕事用パソコン購入など)
4 国民年金を一括納付した領収書があるが、実際には12月末でぬけてしまったので、その金額がややこしい
5 健康保険任意継続も同じ状況
6 医療費還付金がある(たぶん)年末に手術をしたため
7 互助会から医療費の還付がある
手順 イータックスコーナーから
1 パソコンで申告書作成コーナーに行く
昨年のデータがのこっていればそれが使えます
拡張子が[.data]であれば。私はなかったので新規作成です。
あとは指示に従って入力していくだけなんですが、途中で保存してやめることもできます。
注意したいのが「保存する」ボタンを押しただけでは保存されず、確認表示がされるのでさらにもう一度ボタンを押すと、特に指定していなければダウンロードフォルダにはいります。
サラリーマンであればまず所得税の申告書を作ります。
今年だけの注意点として、税金上の扶養ではない子供の申告は通常はしなくてよいのですが、今年に限ってはしなくてはなりません。入力の途中でも注意がでてきますが、ここをわすれると昨年度初めに話題となった定額減税が無駄になってしまいます。
医療費控除
医療費控除は、医療費のお知らせが使えるようになり、ずいぶん便利になりました。
ただ、医療費のお知らせの区切りが年末ではないので、数年前までは、年末までの数か月分は手計算だったのが、マイナポータル連携で年末までの分が分かるようになりました。
私の場合、加入していた保険組合から、付加給付があるのですが、それも掲載されています。
ただ、2月末時点で、前年末の12月の付加給付はまだ決定していなかったのですが、手術をしたので、たぶんでるだろうな、と。保険組合に確認したら、3月半ばには通知が行きます、とのこと。
確定申告に間に合わないのでその時とるべき手段は2つ
1 とりあえず申告し、あとで修正
2 通知を待つ
2の手法に関しては、税金が還付されそうな人はやっても構わない方法です。
追加納税がありそうな人は1の方法をとらないと、ペナルティになります。
私は2の方法にしましたが、結局間に合いました。
さらに互助会から還付金があるのでその分医療費から引いた申告をします。
加入している互助会では、還付金は医療費のお知らせでないとできないので、確定申告の時にはまだ出そろいません。このばあいは12月までの医療費が分かった時点で、計算して提出し、最終的に修正が必要になったらする、という方法がよいでしょう。
社会保険料
これは国民年金も対象です。私のばあいは、4月に一括して1年分納付したので、その領収書はあったのですが、12月までとなると正確なところが分かりません。社会保険事務所に電話して、照明になるような書類を発行してもらいました。
健康保険はこちらも任意継続の掛け金を1年分一括納付していたのですが、1月から3月の分も入っています。私の場合、1月1日に脱退したので、保険組合に電話して、いくら戻ってくるかを確認、納付額から還付額を引いた金額で入力しました。
経費
所得税の申告書ができたら、もう一度申告書作成コーナーに戻り、今度は青色申告書と収支内訳書の作成に入ります。ちなみに白色申告の人も、経費の申告をする場合はここから作成します。
昨年のデータを再利用したり、入力の途中で保存しておくことも可能です。
青色申告は事前に開業届をだし、帳簿のつけ方も難しいですが、経費の計上などで、白色申告よりもメリットが多いといわれますが、収入があまりない場合気にしなくてもよいとは言われます。
経費申告は、会計ソフトを使うと単品でイータックスから提出できるようですが、そうでない場合は、所得税申告書の添付ファイルという形での提出となります。
経費として計上できるものや詳細はネットで調べるとたくさん情報がでてきます。
追加 健康保険について 任意継続か国保か扶養か
会社を辞めたあと、国民健康保険に入るか任意継続するか迷う人は多いようです。
掛け金がどちらが安いか、というのも気になります。
私の場合任意継続の掛け金を計算する方法を保険組合の資料から探し、計算しましたが、役所か社会保険事務所かどっちだったかわすれましたが、聞いたら教えてくれるそうです。
私が任意継続したのは、
人間ドックなどのサービスがよさそうなのと任意継続は退職のタイミングでしかできないという点です。
任意継続はマックス2年。自分の意志で脱退して国保に切り替えることも可能です。
最終的に脱退したのは、人間ドックなどの金額が、保険組合の割引料金と聞いていたのですが、さして安くはならず、しかも、私がここ数年人間ドックを受けていた病院に関しては割引料金がなかった、というところ。ただその時点では付加給付があることに気づいていなかったので惜しかったとは思います。
あとは転職活動がおもうようにいかないということでした。
脱退後
私は家族の扶養に入れてもらいましたが、結論からいうと、扶養に入れてくれる家族がいるなら、絶対に退職の時点で加入しましょう。
私は、退職の時点で家族の勤務先が組織変更して保険証の書き直しも済んだばかり、扶養加入のお願いができないといわれたのと、再就職したばあいまた扶養から外さないといけないのは仕事が増えるからという理由で断られましたが、後になってみればここでもっと周囲を説得すべきでした。
最終的には扶養に入れましたが、退職の時点で加入しない場合不正を疑われたりいろいろと手続きがややこしく、先方から言われた書類が任意継続手続きで使ってしまっていて、用意できないとか、まあ本当に大変です。
あとは、保険加入とか、扶養加入の手続きは前の保険を抜けてからでないとできないのが原則ですが、事前に根まわししないと抜けたのはいいが加入できないということが起きます。特に扶養家族にかんする規定は組合によってちがうので、入れると思っていると大間違いだったりします。
私の場合、失業手当をもらった(手続きの時点では受給がとっくにすんでいたにもかかわらず)
就職活動をしていた
クラウドソーシングサイトに登録して入力の仕事をしていたが、単価が安いため給料として発生していなかった
なんといっても退職時に任意継続の手続きをしていた
こんなことがネックになり、なかなか手続きが進みませんでしたので扶養家族という可能性がある人はそちらを最優先するほうが、ストレスがありません(世の中的にはいろいろな考えがあるでしょうが、あくまで、手続きのことだけを考えた場合のことです)

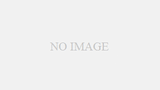
コメント